シハイスミレ(紫背菫)
スミレ科 スミレ属
学名:Viola violaceaa
日当たりのよいやや乾燥気味の山地の林縁などに生えるスミレ。
シハイスミレは、漢字にするとわかりますが、支配ではなく紫の背と書いて「紫背」です。
葉裏が紫色を帯びることからきています。
花も濃い色のものが多く、距も色がついています。
また、花柱の先はカマキリの頭形をしているスミレです。
【撮影カメラ】PENTAX K20D
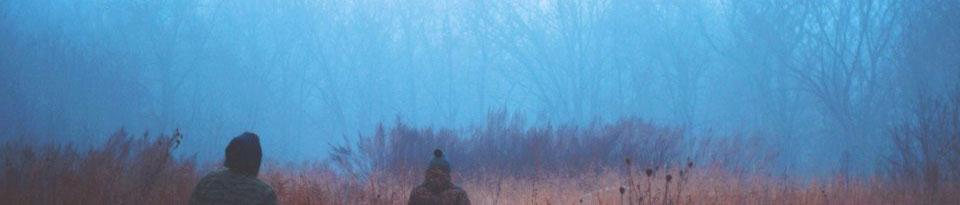
4月 07
シハイスミレ(紫背菫)
スミレ科 スミレ属
学名:Viola violaceaa
日当たりのよいやや乾燥気味の山地の林縁などに生えるスミレ。
シハイスミレは、漢字にするとわかりますが、支配ではなく紫の背と書いて「紫背」です。
葉裏が紫色を帯びることからきています。
花も濃い色のものが多く、距も色がついています。
また、花柱の先はカマキリの頭形をしているスミレです。
【撮影カメラ】PENTAX K20D
8月 31
ミネウスユキソウ(峰薄雪草)
キク科 ウスユキソウ属
学名:Leontopodium japonicum var. shiroumense
別名:シロウマウスユキソウ(白馬薄雪草)
エーデルワイスの仲間であり、ウスユキソウの変種。
エーデルワイスの歌がありますが、こどもの頃、イメージしてた花と違った時の衝撃を今だに覚えていますが、今ではそんなに嫌いではないです(笑)
和名の由来は、葉や花が全体的に白い毛に覆われている様を雪にたとえたことから薄雪草(ウスユキソウ)と名付けられた。
ウスユキソウの和名の付け方はいい感じです♪
8月 31
オオバミゾホオズキ(大葉溝酸漿)
ゴマノハグサ科 ミゾホオズキ属
学名:Mimulus sessilifolius Maxim.
山地の水が流れるような湿性の場所に生える多年草。
和名の由来:ミゾホオズキより葉が大きいことからから大葉溝酸漿と名付けられる。
【撮影カメラ】PENTAX K20D・PENTAX OptioW60
8月 30
ミヤマクワガタ(深山鍬形)
ゴマノハグサ科 クワガタソウ属
学名:Pseudolysimachion schmidtianum ssp. senanense
高山・亜高山の岩場・礫地に生える多年草。
和名の由来は、深山(ミヤマ=高山)に生え、実につく萼が兜飾りの鍬形に似ていることから深山鍬形(ミヤマクワガタ)と名が付いたようです。
ミヤマクワガタと言うと、普通に昆虫のクワガタを連想しそうですよね(;・∀・)
【撮影カメラ】PENTAX K20D
8月 30
キバナノコマノツメ(黄花の駒の爪)
スミレ科 スミレ属
学名:Viola biflora
亜高山帯~高山帯のやや湿り気のある箇所に生えるスミレ。
日本での分布は広いようで屋久島でも見ることができるらしい。。。
和名にスミレの名が付いていないから、名前だけでは何の花?となりそうですが、葉の形が馬の蹄(駒の爪)に似ているところからその名がある。 葉には光沢がなくやや薄いので、花が似ているクモマスミレ(2012年撮影)との区別ができるようです。 ただ、タカネスミレと同居している箇所もあるみたいなので、この種のスミレはしっかり確認しないとダメですねー。
白馬岳遠征では、ここでしか見れてなく、また撮影しづらい場所であったため一枚だけの撮影。。。
いつかまたです。
【撮影カメラ】PENTAX K20D
8月 30
ミツバオウレン(三葉黄蓮)
キンポウゲ科 オウレン属
学名:Coptis trifolia
亜高山帯~高山帯のやや湿った林内や林縁に生える常緑の多年草。
雪解けの早い時期に花を咲かせるミツバオウレンですが、お盆の時期に見れたのは雪渓のおかげかもしれません。 雪渓があるコースだと春と夏の花が一緒に見れるんですよね。
和名の由来は、オウレンに似て、三つ葉をしていることから三葉黄蓮(ミツバオウレン)と名付けられる。
オウレンは、根茎が黄色く太く連なるところから蓮根に見たてて「黄連(黄蓮)」と呼ばれる由来となっているが、元々は中国原産の別種の名前。
【撮影カメラ】PENTAX K20D
8月 28
8月 27
タカネナデシコ(高嶺撫子)
ナデシコ科 ナデシコ属
学名:Dianthus superbus var. speciosus
カワラナデシコの高山型となる。
高山帯の日当たりのよい草地または岩石地に生える多年草。
和名に高嶺と付くように高い山のナデシコという意味ですね。
最初見たときは、花びらが全部縮れているのでもう枯れかけているのかと思ったら、これがふつうの状態だったとは。。
でも、なかなかきれいな状態の花はなかったりしました(^-^;
【撮影カメラ】PENTAX K20D
8月 25
8月 24
モミジカラマツ(紅葉唐松)
キンポウゲ科 モミジカラマツ属
学名:Trautvetteria japonica
亜高山帯~高山帯の湿原や雪田の縁などの湿った場所に生える多年草。
和名の由来は、唐松草(カラマツソウ)全体では、花の姿を唐松(カラマツ)の葉に見立てたことが付いた名であり、単葉でもみじのように葉に切れこみが入っているから、紅葉唐松(モミジカラマツ)と名が付けられる。
【撮影カメラ】PENTAX K20D
最近のコメント